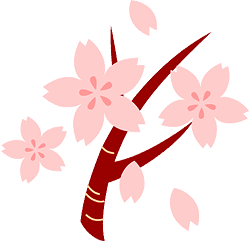| 紅花染め ワークショップの内容 | |||
 ・紅花について 紅花はエジプトや地中海が原産と考えられ、シルクロードを渡って3~6世紀頃に日本に伝わりました。 染め物以外にも、漢方薬や化粧品として使われてきました。 紅花は夏至の頃に花が咲きます。 花の下には棘があるので、朝露に濡れて柔らかい時間帯に収穫します。 紅花の持っている色素のほとんどが(99%)サフロールイエローという黄色の色素。 そして僅かに紅色素が含まれます。 紅花染めはこの僅かな紅を取り出すのと、夏に収穫する花を腐らせず保存させる、そして日本各地に運ぶという難題をクリアしてきた染めです。 収穫した紅花は、水で良く洗い、水に溶けやすい黄色色素を流します。その後数日かけて発酵させて、紅を出します。 臼杵でついて、お持ちのように丸めて乾燥させます。 これを紅餅(花餅)といいこの状態で各地へ運んでいました。 大変に貴重だった紅餅は、一時期では金貨と同価値であった程。  |
|||
| 今回のワークショップではこの紅餅を使います。 紅餅にもまだ黄色色素が含まれています。 この黄色色素を抜くため、1~2日前から水に浸けておきます。 黄色色素は、私が抜き出して当日お持ちします。 今回のワークショップではこの抜いた黄色色素を使って絹の五本指靴下を染めます。 |
 紅色素と黄色色素で染めた絹糸  黄色を抜くところ |
||
| 黄色を抜いた紅餅から今度は紅色素を抜きます。 ここからが今回のワークショップの内容です。 紅色素はアルカリに誘われて出てきます。 鹿児島から取り寄せている木灰でアルカリ液を作り そこに紅餅を投入。紅を抜きます。 紅の溶けた液体に山繭絹のストールを投入。 茶色く染まります。 |
 アルカリで茶に染まる |
||
| 良く染料を絹に染み込ませたら、少しずつ純米酢を加えていきます。 焦らず少しずつ、少しずつ。 アルカリでヌルヌルしている液体が少しずつ少しずつサラサラとして、酢の香りがたってきたころ 絹のストールは紅色に花咲きます。 |
 酢で赤く発色  乾くと桃色 |
||
| 染め全体を通して、冷たい水が色をきれいにするのに必要。 冷たい水は、冬の風。寒さを我慢していると、 本当に素敵な花と出会えるという 楽しい染めです。 当日はもう少し紅花の事もデジタル紙芝居でお伝えしたいと思います。 |
 素材によって染まり方も異なります。 |
||
前回の藍の生葉染めワークショップの様子  会場も同じ香川公民館 |
|||